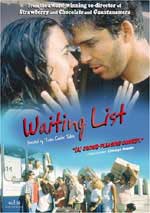
2005年その10
ニュージーズ Newsboys (NEWSIES) (1992年アメリカ)
とほほほ・・なんだかノリの悪い音楽と踊りのディズニーミュージカルなのだが、 若きクリスチャン・ベールの甘切なまなざしと口元がね、いいんです。 バットマン・ビギンズを見てから、このDVDを見た人とか多くない? みーはー気分でみれば、、、あぅ、あの「ぼっちゃま」の少年時代ってこんなんなのね〜 と、大いなる勘違いをしまくり、思わず「ぼっちゃま、がんばれ〜っ」と応援のこぶしにも 力が入る(笑)。 1899年にNYで起きた新聞売り少年たちのストライキを基にしたミュージカル。 当時、新聞は100部50セントで少年たちに卸していた。買取制なので売れ残っても 払い戻しは無い。新聞社主たちは新聞代は値上げせずに、卸値を100部60セントに しようとしたため、少年達は団結してストライキに入った。 悪い奴はとことん、わる〜い顔をしているし、恥ずかしいほどお約束物で、 最悪なのはロバート・デュパル。こんなしょーもない役を演じていたとは。。 「ウォルター少年と、夏の休日(セカンドハンド・ライオン)」で名演技をみせて くれたロバート・デュパルとマイケル・ケインコンビが、かたや「ぼっちゃま」を 助け、かたや「ぼっちゃま」を苛めていたんですね〜・・って(違うっ! 笑)。 (2005.08.02) ------------------------------
スター・ウォーズEP3/シスの復讐 Star Wars Episode III - Revenge of the Sith(2005年アメリカ)
8月の優待券がムダになってしまうっ、と慌てて最終日に見に行った。 先行上映で見た息子は、めまぐるしい画面転換に気分が悪くなり、わけもわからんかった、と 情けない感想を述べていたが、確かに贅沢きわまりない紙芝居だ。これほど短い場面に それほどお金をかけなくても・・と言いたくなるほど、多くの舞台があっさりと切り替わる。 そんで、そんで、そんで、と、読み聞かせの物語を楽しむように見るのがコツだろう。 まさに神話やギリシア悲劇や昔話の、約束世界なのだ。 その世界をここまでこだわって作ってくれた監督に感謝したい。 近代以降、国や反乱軍、テロ集団の戦いにおいて、リーダー同士の戦いなどありえない。 各リーダー達は政治的な場でしか対面しないとおもう・・んだが、 かくも超近代兵器を揃えた軍隊が宇宙を飛び回っているというのに、スターウォーズでは リーダーがほいほいと一騎打ちする。 一番知恵や力、技をもつものがリーダーだ、という、わかりやすい社会(笑)。 リーダーの一騎打ちは、光と闇、善と悪、天使と悪魔、をこれまたわかりやすく象徴する。 ほんまにスペシャルハイクォリティ紙芝居なんだよねぇ。 そんな目でみていたからか、どの場面だか忘れてしまったが、一瞬ドラクロアの 『天使と闘うヤコブ』の絵を彷彿させる映像があり、あの組み手は!とハッとした(笑)。 さて いろいろあったが、実はわたしは単純にも泣いてしまった。 心の闇に食われてしまったアナキンがあまりに哀れだった。 I hate you!と叫ぶ姿。 ダースベイダーのあの鎧は、赤く焼け爛れた皮膚を保護しているように 心の苦痛を押し込めているんだわ、、などとおセンチになってしまった。 暗黒時代の到来と、未来へ託された希望・・ シリーズの終りにふさわしかったね。 (2005.08.30) ------------------------------
幸せになるためのイタリア語講座 Italiensk for begyndere(2000年 デンマーク)
ハナマル。 人工照明を使わない、手持ちカメラだけで撮影する、役者が自分でメイクする、、といった デンマークのドグマ集団のロネ・シェルフィグ監督の作品。 ベルリン国際映画祭銀熊賞受賞。 ドグマというと、実験的で船酔い系映画、という印象が強くて、最初、え?失敗だったか、と 思ってしまったが、それはわたしの思い込みだった。 惨めで残酷で滑稽で、孤独な日々をおくっている男女が、それぞれの理由から 初心者向けのイタリア語講座に通いだす。 看護婦、パン屋の店員、ホテルのフロント、牧師、元レストラン店長、不動産業・・、 週に一回のイタリア語講座を人生の交差点のように、巧みに使う。 陽が短く陰鬱な北ヨーロッパの人々にとって、イタリアは「光の世界」を象徴しているのだろう。 イタリア語講座に通う人々は、誰もが社会とあまり上手くやってゆけてない。 愛する者を失ったり、性的不能だったり、軽度の学習障害だったりするが、 イタリア語がしゃべれれば、自分の殻からぬけだせる気がしている。 普通の人々がそこに居て、普通に不幸な日々をおくっている。 これが実によくわかる。 そして、悲しい出来事と小さな奇跡が起こり、ぬくもりと慰めが待つベネチアへ彼らをいざなう。。 決してじめじめせず、ユーモアに満ちているのが良いところで、単純にファンタジーといって 片付ける話でもない。小さな一歩を踏み出すことが「光」なんだなぁと、癒される物語だ。 さて、特典のメイキング映像を見て、とても不思議な気分になった。 なぜなら、一番寡黙で敬虔にみえた牧師役の男優の素顔が一番ワルっぽく、 一番ワルっぽくて乱暴にみえた元レストラン店長役の男優は、一番生真面目だったからだ。 役と印象が正反対! キャスティングするのって、ほんま、面白い作業だろうなぁ。 #ワルっぽい元店長、すげーナイスなんだよぉ〜。これぞHQヒーローって感じなんだ(^m^) (2005.09.11) ------------------------------
アメリカン・サイコ American Psycho(2000年アメリカ)
物議をかもしたベストセラーの映画化だが、たぶん、元の本のほうが良いんだろうな。 この映画の面白さは、(面白さと言うと顰蹙を買うかもしれないが) クリスチャン・ベールの怪演に尽きる。 ほんま、凄いよ、あんた。まじでヤバイ人じゃないの? 完璧主義者な俳優ってこえ〜よ。。 と、たぶん、観た人は思うよねぇ? ほとんどガキのレベルの「僕のほうが凄いの、持ってるもーん!」 服やカバンのブランド、暮らすコンドミニアム、フォントと紙質と色に命を賭ける名刺、 高名なレストラン「ドーシア」に予約が取れるかどうか。。愚かしい狂気っぷりが実に面白い。 お肌のお手入れ、エクササイズ、めくるめくナルシズムに満ちた生活だが、ただただ退屈である。 空虚な退屈さで育つ暴力と殺人への欲望。 これもまた驚くほど幼稚性に溢れている。ぐっちゃぐちゃに、コミックスのように、 わざとらしい道具で殺したいのだ。 最初から、何か変だった。完全犯罪を目指すサイコキラーではない。 神経質なくせに、ぞんざいな殺人で、進退窮まると、泣き出す幼児なのだ。 だが、さらに震撼とさせて、嫌な気分にわたしをさせたものは、、 (以下はネタバレになるので、白い字に)
これらが空想の産物なのか、現実なのかわからない、という終り方で、かつ どっちでも構わない、という終り方だ。 パトリック・ベイルマンという人物は実在したのか、「おい、デイヴィット」と弁護士から 呼ばれるが、彼は実はデイヴィットという人物なのだろうか? 一体、この話は最初から最後まで主人公の妄想だったのか。 彼の犯した大量殺人は本当に行われたのか。 死体や血のしみが無くなっていて、殺人があったかどうかもわからない。 そう、それらは結局どうだって良いのだ。。 彼は弱い人間(ホームレス、娼婦、老人)を無差別に殺したが、罪を懺悔しようにも 誰も気に留めない、という結末なのだ。 自分が狂っているのか、みんなが狂っているのか、 殺人すら、ブラックホールに飲み込まれていく。。 この空虚な現実感こそが、アメリカンサイコだと言いたいのだろう。 でもこのスプラッターな殺戮は、ライバル視しているヤッピィひとりを除き、 下層の人間ばかり狙われて、しかも殺されたヤッピィも上層とはいえユダヤ人なんだよね。 そう、エリート白人からみた『社会のゴミども、逝ってよぉーし!』、鼻持ちならない高慢さがある。 画面に登場するアジア人は、召使か小人のような、みっともなさだったしね。 人を殺したって、退屈な日常なんだよぉ〜、とアンタに言われたかないっ、同類をひき肉にしてから言ってくれっ
この点が、わたしが下品なブラックジョークだと感じる所以である。 (2005.09.13) ------------------------------
The Waiting List Lista de espera(2000年キューバ・スペイン・フランス・メキシコ・ドイツ)
邦題「バスを待ちながら」で日本でも2002年に公開されたが、DVD化されてなくて、 どうしても観たくて英語字幕DVDを購入。 「苺とチョコレート」の監督、主演コンビだが、いちご・・より政治色を薄めてユーモアで くるんでいる。このオカシミがたまらなく良い。人間の繰り広げる悲喜こもごもを 温かい目で見つめながらも、キューバ社会の問題をしっかりと見ていると思う。 ま、小難しいことを考えずにエンターテイメントとして観てみよう! 舞台は、とある田舎の長距離バスステーションだ。 来るバスはいつも満員で、乗れるのは一人だけ! んなバカなっ、こんなにいっぱい バスを待ってるんだぞ〜っ! いやはや、ごちゃごちゃ、人間がいる。列もつくらずに、あちこちで待っている。 もう2日も待っているのよ!! 誰が列の一番最後? (って列なんて無いだろー) 半分は西のハバナに行きたくて、半分は正反対の東のサンティアゴに行きたい。 ここのステーション所有のバスがあり、偶数の日はハバナ行き、奇数の日はサンティアゴ行き、 と決まってるんだが、バスは故障していて修理中。ようやく「直ったぁ」と言った時、 「今何時?」 「11時56分よ」(夜の) みたいなベタなくすぐりがあるが、、話は意外な方へと進展し、奇妙な味わいの わくわくする人間ドラマになってゆく。 わが国が誇る?「幽霊電車」(1949)となんだか雰囲気が似ている、待合所の怪(笑)。 バスを待つ人々それぞれが背負った人生があり、寂しさ、ズルさ、弱さ、強さ、が バスステーションの魔法の帽子の中にひとたび入ると、そこには・・・。 個人主義と同時に共産主義をも皮肉りながらも、人間どおしが助け合う優しさを 心温かく描き、泣かせてくれる。 ほろ苦い現実のあとに呼びかけてくれる声がある、そのラストの希望がとても嬉しい。 (2005.09.19) ------------------------------
ストレート・ストーリー The Straight Story (1999年仏・英・米)
デビット・リンチ監督。実話に基づいた映画らしい。 男のロマン。 ま、女も少しは出てくるが、「男の夢」の映画だなぁ。 73才、ジイサン500Kmひとり旅。 10年間仲たがいをしている兄が卒中で倒れたと聞き、芝刈り機を改造して、500km離れた 隣の州の町まで旅をする。同居する娘のエピソード、旅の途中で出会う10代の妊娠や 若者の傲慢や、人生の悔恨などなど。 アメリカの広々と広がる農地、頭をたれる穂、大地の豊穣に感謝し、命の営みに感謝し、 愛する家族や兄弟と思い残さずに大往生したいと願う気持ちを淡々と描いている。 まさにストレートな物語。ゆっくりした生き方を忘れがちな現代に贈る物語。 俳優が上手いし、ストレートな話だし、ケチのつけようがない。 よくも悪くも、スタバーンを感じさせられる映画だった。 HQを読んだ事がある人ならきっと分かると思うが、しばしば主人公たちの「stubborn」に 呆れるのだ。なんてかたくななんだ!と頭にきてしまうことがある。 日本人には想像つかないほど彼らはスタバーンで、人の手助けや勧めや助言を断り、 自分ひとりの力でやろうとする。そして、その Stubborn は賞賛に値しこそすれ、 非難されることはない。「個人」の意識の違いをStubbornを見るといつも感じる。 (2005.09.25) ------------------------------
ブギー・ナイツ Boogie Nights (1997年アメリカ)
ポール・トーマス・アンダーソン監督。 この映画のDVDを借りる動機は2つあった。まず、アクターズスタジオでジュリアン・ムーアと リプトンさんがPTアンダーソン監督を激賞していたこと、もうひとつは、見ようと思っていた 「ワンダーランド」の主人公が、この映画の主人公のその後(正確にはこの主人公のモデルと なった男のその後)を描いたものだということで、興味を引かれたのだった。 で、この映画は、、、エエ加減で猥雑で情けなくておもしろうてやがてかなしき・・・? 70年〜80年代のポルノスター『ジョン・ホームズ』が主人公のモデルだ。 って、わたしはこのあたりの洋物ポルノ映画を何一つ知らないし、この頃の洋楽も全く無知だ。 だが同時期に青春期を過ごしたものとして、知らない世界なのに同時代性を感じる。 その頃、日本でも日活ロマンポルノとかポルノって言葉が市民権を得て、「いかがわしい」ものと、 オモテの世界の境が混沌としだした時期で、でも、まだ「いかがわしさ」という隠花の美が あったような感じで、今のアダルトビデオとかとはちょっと違う、フィルムの時代があった。 主役の男優は、個人的にはちょっとイケテナイんだが、それがまたポルノスターに合う感じ? ポルノ映画監督ジャック役のバート・レイノルズがぴったりはまっていて、ポルノクィーンのJ・ムーアも まさに大地母神。ほかのキャスティングも笑えるほどぴったりだ。 ポルノ映画製作「ジャック組」の面々の、人生浮き沈み、ごった煮群像劇で、救いが無いような あるような、好き嫌いが分かれる映画かもしれない。 アレが大きい事が売りのエディ(芸名ダーク・ディグラー)なんだが、最後の落ちまで情けなくて、 この脱力感あふれる優しさがこの監督の売りなのかなぁ。。 見終わった後で、「パンチドランク・ラブ」がPTアンダーソンだったことに気がつき、 あの「トイレの掃除道具」といい、この映画のイチモツといい、妙に情けないものが主役なんだ(笑)。 #さて、このイチモツなんだが、映画のセリフによると13インチだというのだ。 32.5cm ! 一体そんなものが下着の中におさまるのであろうか? 真剣に考えてしまう(笑)。 エディ役を演じたMark Wahlberg はカルバン・クラインの下着のCMをやったモデルだそうで、 たしかに上半身のシャープな筋肉と、妙にもっこりした下着姿が見る者を納得させる。 そして、映画の最後にその正体がモザイクで登場するんだが、う〜〜むむ、本物なのかなぁ。。(爆) (2005.09.25)
シネマに戻る ホームへ戻る