2006年その5
アイズ・ワイド・シャット Eyes Wide Shut
(1999 アメリカ)
キューブリック監督、トム・クルーズ、ニコール・キッドマン、、豪華です。
スクリーンが映画というより絵画です。
時間が空いたからといって、ぼけっと見るには向いてませんです。
現実に対しては「夢だと思え」「深刻に考えるな」「忘れろ」なのに
夢に対しては、現実が脅かされる恐怖を感じる。
でも、脅かされる現実って何?
って問いに「ファックよ」
そーなんすか。人生やっぱヤル以上のことって無いんですねぇ。
それとも「クソよ」って訳すのかな? 人生なんてクソだってこと?
暗号を解くつもりで、アレはこういう意味で、アレはあれの象徴で、と誰かから
教えてもらわなければさっぱり分からないワタシに、
「ファック --> バカタレ」 と言ってるんでしょーか。
(2006.05.14)
----------------------------
ドラム・ライン Drumline
(2002 アメリカ)
フットボールの試合のハーフタイムに繰り広げられるマーチングバンド合戦。
こんなにすんごいとは、知りませんでした〜。
ストーリーはあまりに単純なスポ根系ですが、この美技をみるだけで楽しいっす。
バンドキャンプと呼ばれるしごき合宿に始まり、最大の山場ドラムバトルで終わる。
王道中の王道。
でも魅せられます。
(2006/05/17)
----------------------------
ゲーム・オブ・ライブズ THE GAME OF LIVES
(2005 アメリカ)
1950年ブラジルWCで、アマチュア選手の寄せ集めアメリカチームが
優勝候補だったイングランドを無得点に押さえ一勝をあげたという実話に基づいた映画。
資金がなかなか得られず低予算となり、選手それぞれのエピソードを切り詰めねば
ならなかったそうだが、物語の底流に確とした愛情があり、この人生の一こまが
限りなく美しい。
日本のDVDではジェラルド・バトラー主演「ゲーム・オブ・ライブズ」と銘打ってあるが、
確かにジェラルド・バトラーと書いてなきゃ見ようと思わなかったかもしれん。
低予算映画に彼が出演を承諾したってことが、ちょいと嬉しかったりもする。
これはアメリカにおける意外なスポーツ史なんじゃないだろうか。
サッカーにこれほど打ち込んでいた人々がいたということ。
ブラジルWCで一勝をあげた歴史をもっていること。
イタリア移民やドイツ移民、ハイチ移民など、それぞれの文化背景とアメリカ人としての誇り、
これらが2週間のあいだにほどよく融合してゆくのが、お約束の映画だとわかっていながらも
ちょっとうるうるとくる。
サッカー競技として見てもかなり面白い。
イングランドに勝つためにフォーメーションを変え、もぎとった1点を守り抜くための
言葉が「スタミナ」。
後半の必死な守備は手に汗を握る展開。
この大会でアメリカはスペインに3−1、イタリアに9−0で負けたそうだが
それでもこの快挙は色褪せない。
このときのメンバーはその後サッカーコーチとなった者もいれば、家業を継いだ者もいる。
そのあたりのエピローグが上手くまとまっていたらもっと良かったんでは?と思うが
けっこう唐突に終わる。たぶん予算上の問題があったのだろう。
セントルイスの町Hillで2000年に行われた式典の様子がこちらにあるが
それも映画とあわせて見ると良い感じ。
#GKフランク(バトラー)、鉄壁!うをっ最後の砦! 神がかっております。
バトラー自身はずっとFWだったそうですが、GK似合ってますね〜。
#ウォルター・バー役のウェズ・ベントレイって、前にみた「サハラに舞う羽」の
あのジャックなのね、、いつも微妙なポジションだがこっちの役のほうがずっと良いわねぇ。
(2006/07/08)
----------------------------
M:i:3
(2006 アメリカ)
これはトム・クルーズの、トム・クルーズによる、トム・クルーズのための映画である。
やっぱりしあわせってのは愛する普通の女性と家庭を築くことだ! と、
小市民的しあわせを手に入れようとしたイーサン=トムが、愛する女性を守るため
はしーる、かけーる、ころーぶ、おちーる、はしーる、とぶ、はしーる、はしーる、、
そう、とにかく走るんである。
当初のミッション・インポシブルは、知的スリルがあったはずだが、
このミッション・インポシブルにはオツムはあまり必要ない。
肉体あってこそのミッション敢行! 中年にさしかかった体にムチ打ってがんばります。
正体のわからない黒幕も最後近くまでは冴えていたんだが、最後になってオバカさん。
テレビの時代劇によくある「死ぬ前に聞かせてやろう」的なお約束、
のこのこと姿をあらわし、バカな言動をとる。
ま、いいんです。予定調和なんですから。
無理やり難問をつきつけたわりに、腰砕け脚本だと思わなくもないが、
いいんだ、オツムは必要ないんだからサ。アクション&ラブを楽しめば。
MI-2よりはよく出来ていたと思うが、そういえばあれも最後の対決がしょぼかった(笑)。
音響がすごく良いので、横でしゃりしゃりポップコーンを食べている人がいたとしてもOK。
「いよっ!イーサン、がんばれー!」と叫んでも、自分の声も聞こえない。
けなしているように書いてるけど、けっこう楽しめましたよ♪
(2006/07/11)
----------------------------
サッカー小僧 Fimpen
(1973 スウェーデン)
とってもオカシナ映画である。←誉めているつもり。
スウェーデンって不思議な国だ。子供を主役にした映画が実に秀逸。
どこが秀逸か、というと、子供もひとりの独立した人間として扱っているからなんだろう。
わずか6才の天才サッカー少年が代表チームに加入し、WC欧州予選を戦うって話だが、
日本で同じネタで映画をつくってもこうはならないだろう。
字も習っていないような子供だが、自分の事は自分で決定する。
親や教師もとやかく言わない。
代表チームの練習に参加すること、試合に出ること、代表チームから脱退すること、
すべて6才のヨーハンが自分で決める。
WC出場をかけた大事な試合でも送迎もなく、ヨーハンは自分ひとりで出かけたりする。
意思は大人同様にはっきりと表明するが、あくまでも子供で、
スパイクの紐が上手く結べないし、アウェイの試合では寝付かれないし、
子猫に夢中になって試合を忘れたりする。
かわいげもあまり無くて、ぶっちょ面をしてるのが実にいい。
妙に淡々としているが、すんなりと信じてしまいそうになる話だった。
よく考えると「少林サッカー」よりも荒唐無稽なのに、CG無しで十分に魅せられてしまう。
これって監督の撮影に仕方が上手いのかな?
74年のWC西ドイツ大会に出場したスウェーデンチームの本物が出演してるってのも面白い。
当時は、あのピチパン。
やってるサッカーも、ちょっともっさい。現代サッカーのスピード、組織的守備とは
ずいぶん違う。
だが、ウイングのヨーハンへのパスを彼が柔らかくトラップしてクロスを上げたり、
ゴール前に駆け込んでくる様子など実にうまくて驚いてしまう。
ヘディングシュートなんて、真面目に考えると6才の子供なら脳震盪起こすだろっ!
って感じなんだが、うわー!と喜んでしまったりする。
当時のソ連、レーニンスタジアム(収容人数10万人)が見れるし、
当時の代表監督や代表選手が自然な演技をしてるのもおもしろいし、
なによりスウェーデンの普通の町並をみるのもおもしろい。
#ドイツのとあるサイトが、この映画はコメディのように見えるが、
色々な問題を投げかけていると書いていた。
わたしたちはこの映画を見ると、6才の子供だって?アホらしい〜、と
子供と大人のあまりの違いに笑うが、第3世界ではこのぐらいの年齢の子供達も
重労働についていたり、一家の生計を支えたりしている。
またアフリカでは近年少年兵の問題も深刻になっている。
サッカーだとこんなにアホらしく感じる事が、実際まかり通っている現実がある。
競争世界に幼い子供が身を投じる愚かしさをクスクス笑ってみていたが、
日本のお受験を思い浮かべると笑ってばかりいられないか。。
(2006/07/12)
----------------------------
コーラス Les Choriste
(2004 フランス・スイス・ドイツ)
世界的指揮者が母親の訃報をうけて故郷に帰り、そこで何十年ぶりに友に会い、
子供時代のひとりの教師との出会いを回想する・・・
時は第二次世界大戦の痛手がまだ癒えぬ1949年、孤児や問題児を収容する
寄宿学校にひとりの教師がやってくる。
「池の底」と呼ばれるこの陰鬱な学校でくらす子供達の大半は親に捨てられた
子供たちであり、その教師は舎監の仕事も兼ねていた。
学校モノの王道なのだが、過剰な涙や笑いを要求しない、その品の良さがとても心地よい。
日本だったら、楽譜を持つ係りなど屈辱的じゃないか?と思ったりするが、
それはそれ、人にはそれぞれ得手不得手があると、さっぱりしたものだ。
映画は音楽のもつストレートな力を全面に押し出してはいるが、同時に、
教師マチュー自身の孤独もほろ苦く切なく描き、味わい深いものにしている。
紙飛行機とバス停シーンでは、わかっていても涙が。。
それぞれの人生に幸あれ、と思わず祈りたくなる映画だ。
(2006/05/01)
----------------------------
そして、ひと粒のひかり Maria Full of Grace
(2004 アメリカ・コロンビア)
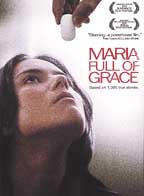 近年日本でも話題になる、体内にドラッグを詰めて密輸する運び屋の物語。
イエス・キリストの母マリアの処女懐胎にもひっかけてあるんじゃないかと思う題。
ヒロイン、マリアはコロンビアのバラ工場で働く。
一日中立ちっぱなしでバラのとげを取り、箱詰めをして、アメリカに輸出する。
安くて過酷な単純労働、でも、これしか労働需要がない。
需要と供給の資本主義社会に組み込まれたまずしい南米の国の日常。
考えてみると、バラとドラッグになんら違いはない。
どちらも、輸出用の、世界経済に組み込まれてしまった需要だ。
運び屋のコロンビア側元締めに限らず、
コロンビア人たちのドラッグに対する感情は冷めている。
それは危険な麻薬ではなく単なる換金商品だ。
映画はサスペンスフルではあるが、意外と静かに進み、終わる。
う〜ん。。
ハイリスク・ハイリターンの仕事しかないコロンビアや
麻薬問題の根の深さを考えさせられはしたが、それよりも、どんなことがあっても
女は生きていく、結局、ヤバイ仕事でもやってみたもん勝ち、、って印象が否めない。
新たな道を歩みだすマリアを待つのは、不法移民の道だ。
それでもアメリカにはまだ夢と希望がある、と映画は言う。
嫌味なくらい、コロンビアに戻るブランカは、ブスで進歩がなく自分勝手で、
一方、アメリカに希望を見出すマリアは、美人で勇敢で誠実である。
アメリカは今後も、ドラッグと不法移民があとをたたないだろう。
需要があるかぎり、入りつづけるだろう。
そして思ったのは、日本のことだった。東南アジアからの不法滞在者やドラッグ密輸が
もっともっと問題になるのは遠い先のことでもあるまい。
そうしたときに、マリアの勇気に共感した気持ちを皆が思い出せるのだろうか。
(2006/07/17)
----------------------------
近年日本でも話題になる、体内にドラッグを詰めて密輸する運び屋の物語。
イエス・キリストの母マリアの処女懐胎にもひっかけてあるんじゃないかと思う題。
ヒロイン、マリアはコロンビアのバラ工場で働く。
一日中立ちっぱなしでバラのとげを取り、箱詰めをして、アメリカに輸出する。
安くて過酷な単純労働、でも、これしか労働需要がない。
需要と供給の資本主義社会に組み込まれたまずしい南米の国の日常。
考えてみると、バラとドラッグになんら違いはない。
どちらも、輸出用の、世界経済に組み込まれてしまった需要だ。
運び屋のコロンビア側元締めに限らず、
コロンビア人たちのドラッグに対する感情は冷めている。
それは危険な麻薬ではなく単なる換金商品だ。
映画はサスペンスフルではあるが、意外と静かに進み、終わる。
う〜ん。。
ハイリスク・ハイリターンの仕事しかないコロンビアや
麻薬問題の根の深さを考えさせられはしたが、それよりも、どんなことがあっても
女は生きていく、結局、ヤバイ仕事でもやってみたもん勝ち、、って印象が否めない。
新たな道を歩みだすマリアを待つのは、不法移民の道だ。
それでもアメリカにはまだ夢と希望がある、と映画は言う。
嫌味なくらい、コロンビアに戻るブランカは、ブスで進歩がなく自分勝手で、
一方、アメリカに希望を見出すマリアは、美人で勇敢で誠実である。
アメリカは今後も、ドラッグと不法移民があとをたたないだろう。
需要があるかぎり、入りつづけるだろう。
そして思ったのは、日本のことだった。東南アジアからの不法滞在者やドラッグ密輸が
もっともっと問題になるのは遠い先のことでもあるまい。
そうしたときに、マリアの勇気に共感した気持ちを皆が思い出せるのだろうか。
(2006/07/17)
----------------------------
狩人と犬、最後の旅 Le Dernier Trappeur
(2004 フランス、カナダ、)
カナダ・ロッキーで狩りで生活をたてている人々の暮らしを約1年間おった
ドキュメンタリー風映画。
実在の狩人ノーマンの体験を元に、本人たちが出演しているわけだが、
どうやって撮影したんだろうとニコラス・ヴァニエ監督の情熱にも感心する。
フランスにはこのような映画がいくつも見受けられるが、商業的に成り立つのが
不思議でならない。なぜ日本では出来ないのか、この違いは何なんだろう。
ここでは狩人も自然の中の食物連鎖の一員になっている。猟をすることで野生動物の
増えすぎを抑え、自然のバランスに一役買っていると自負するノーマンだが、
すすむ伐採や開発により狭まる猟場。もはや狩りは続けられないと悩むノーマン。
きれいだな〜、雄大だな〜、冷房の効いた映画館で見ている分には気楽な映画だが、
自然のバランスに則って生きるには、これほどの厳しさを覚悟しなければならない、
と考えると、根性の無い人間が地球上に増えてゆくのは仕方ないことかもしれない。
どんどん地球の奥地まで人間は侵食してゆく・・・
となかいの大群を見れただけでも、この映画を見た甲斐があった。
(2006 8/20)
----------------------------
ダック・シーズン Temporada de patos
(2004 メキシコ)
 みて大正解の映画! スタイリッシュな映像と、静かに胸にしみる優しさ。
日本の小津監督を尊敬しているそうで、そういう感じはよく伝わる。
でたらめで生真面目。
なんのへんてつもないようで、とってもオカシイ。
大人の責任もない、将来や仕事、お金の心配もしなくてよい、恋とか愛とか
女の子にもまだあまり興味がない、でも、もう子供でもないし、いろんな不満につぶされそう、、
そんな14才の、単純でいて複雑な「時」を掬い取っている。
留守番をまかされた14才の少年ふたり。
お菓子を食べながらテレビゲームに興じ、母親が置いていったお金でピザを注文する。
隣に住む娘がオーブンを借りに来る。
30ぐらいのピザ屋の配達人が居座る(少年たちがいちゃもんをつけて、料金不払いを告げたから)
日常の怒りや緊張、ぎこちない4人のあいだにコミュニケーションが生まれる過程が
心憎いほど上手い。
わざとらしくなくていつのまにか映画にひきずりこまれる。
この午後が無かったら、主人公の少年は、全く違う大人になるだろうなあ。
この午後が無かったら、彼は嫌なかんじの若者になるんだろうなあ・・
カモの絵はトラブルの元であり、かつ、幸せと希望と夢の象徴だ。
ピザ配達人さんの幸せを心から願うよ〜!
おかあさんの登場する最後がまた笑える。
#十三の第七藝術劇場で11人の観客。。あぁ、もっと多くの人に見てもらえたら。
無理やり(笑)友人をひとり連れていったが、気に入ったらしく
ふふ、ラテンアメリカ映画、布教1。
(2006 9/3)
----------------------------
みて大正解の映画! スタイリッシュな映像と、静かに胸にしみる優しさ。
日本の小津監督を尊敬しているそうで、そういう感じはよく伝わる。
でたらめで生真面目。
なんのへんてつもないようで、とってもオカシイ。
大人の責任もない、将来や仕事、お金の心配もしなくてよい、恋とか愛とか
女の子にもまだあまり興味がない、でも、もう子供でもないし、いろんな不満につぶされそう、、
そんな14才の、単純でいて複雑な「時」を掬い取っている。
留守番をまかされた14才の少年ふたり。
お菓子を食べながらテレビゲームに興じ、母親が置いていったお金でピザを注文する。
隣に住む娘がオーブンを借りに来る。
30ぐらいのピザ屋の配達人が居座る(少年たちがいちゃもんをつけて、料金不払いを告げたから)
日常の怒りや緊張、ぎこちない4人のあいだにコミュニケーションが生まれる過程が
心憎いほど上手い。
わざとらしくなくていつのまにか映画にひきずりこまれる。
この午後が無かったら、主人公の少年は、全く違う大人になるだろうなあ。
この午後が無かったら、彼は嫌なかんじの若者になるんだろうなあ・・
カモの絵はトラブルの元であり、かつ、幸せと希望と夢の象徴だ。
ピザ配達人さんの幸せを心から願うよ〜!
おかあさんの登場する最後がまた笑える。
#十三の第七藝術劇場で11人の観客。。あぁ、もっと多くの人に見てもらえたら。
無理やり(笑)友人をひとり連れていったが、気に入ったらしく
ふふ、ラテンアメリカ映画、布教1。
(2006 9/3)
----------------------------
カクタス・ジャック Matando Cabos
(2004 メキシコ)
 すげぇメキシカン!
ぎんぎんに荒く激しく、まったりもったりと脱力して。
「ダック・シーズン」は、日本でも作れる映画だけれど、これは絶対に日本じゃありえん。
誰もが恐れる財界の大物、オスカル・カボスがゴルフボールを踏んでひっくり返り、
脳震盪を起こしてしまったことから、てんやわんやの物語が始まる。
タランティーノのレザボア・ドックスやパルプ・フィクションをわたしは思い出したが、
タランティーノほどスタイリッシュではない感じ。
むちゃくちゃで、なんでもアリで、ベタな笑い満載、
日本では差別表現になりそうな苛めや、下ネタで笑わせる下品さ。
生々しい残虐シーン、いっちゃってる人たち、
すまんです、わたし、けっこうこういうのが好きで、、ひぃ〜っひっひ、大笑いしてしまったが
館内で笑っていたの、わたし以外はみんなラテンアメリカ人かも?(爆)
よくある「取り違え」ものなんだが、これが実におかしく感じるのは、
いかにも物語!って感じの語り口と、脱力ふたり組がいいんです。
ジャックと、彼の親友のムド。 このふたりが深刻な状況なのに妙にまったりしていて(笑)。
無関係な人が巻き込まれて、殺されちゃったり、ひどい目に合ったり、、
ま、この映画に正義を求めちゃいかんです。。
たぶん、そこら辺が気になる人は、この映画を見たら嫌〜な気分になるでしょう。
(2006 9/8)
----------------------------
すげぇメキシカン!
ぎんぎんに荒く激しく、まったりもったりと脱力して。
「ダック・シーズン」は、日本でも作れる映画だけれど、これは絶対に日本じゃありえん。
誰もが恐れる財界の大物、オスカル・カボスがゴルフボールを踏んでひっくり返り、
脳震盪を起こしてしまったことから、てんやわんやの物語が始まる。
タランティーノのレザボア・ドックスやパルプ・フィクションをわたしは思い出したが、
タランティーノほどスタイリッシュではない感じ。
むちゃくちゃで、なんでもアリで、ベタな笑い満載、
日本では差別表現になりそうな苛めや、下ネタで笑わせる下品さ。
生々しい残虐シーン、いっちゃってる人たち、
すまんです、わたし、けっこうこういうのが好きで、、ひぃ〜っひっひ、大笑いしてしまったが
館内で笑っていたの、わたし以外はみんなラテンアメリカ人かも?(爆)
よくある「取り違え」ものなんだが、これが実におかしく感じるのは、
いかにも物語!って感じの語り口と、脱力ふたり組がいいんです。
ジャックと、彼の親友のムド。 このふたりが深刻な状況なのに妙にまったりしていて(笑)。
無関係な人が巻き込まれて、殺されちゃったり、ひどい目に合ったり、、
ま、この映画に正義を求めちゃいかんです。。
たぶん、そこら辺が気になる人は、この映画を見たら嫌〜な気分になるでしょう。
(2006 9/8)
----------------------------
シネマに戻る
ホームへ戻る
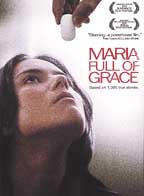 近年日本でも話題になる、体内にドラッグを詰めて密輸する運び屋の物語。
イエス・キリストの母マリアの処女懐胎にもひっかけてあるんじゃないかと思う題。
ヒロイン、マリアはコロンビアのバラ工場で働く。
一日中立ちっぱなしでバラのとげを取り、箱詰めをして、アメリカに輸出する。
安くて過酷な単純労働、でも、これしか労働需要がない。
需要と供給の資本主義社会に組み込まれたまずしい南米の国の日常。
考えてみると、バラとドラッグになんら違いはない。
どちらも、輸出用の、世界経済に組み込まれてしまった需要だ。
運び屋のコロンビア側元締めに限らず、
コロンビア人たちのドラッグに対する感情は冷めている。
それは危険な麻薬ではなく単なる換金商品だ。
映画はサスペンスフルではあるが、意外と静かに進み、終わる。
う〜ん。。
ハイリスク・ハイリターンの仕事しかないコロンビアや
麻薬問題の根の深さを考えさせられはしたが、それよりも、どんなことがあっても
女は生きていく、結局、ヤバイ仕事でもやってみたもん勝ち、、って印象が否めない。
新たな道を歩みだすマリアを待つのは、不法移民の道だ。
それでもアメリカにはまだ夢と希望がある、と映画は言う。
嫌味なくらい、コロンビアに戻るブランカは、ブスで進歩がなく自分勝手で、
一方、アメリカに希望を見出すマリアは、美人で勇敢で誠実である。
アメリカは今後も、ドラッグと不法移民があとをたたないだろう。
需要があるかぎり、入りつづけるだろう。
そして思ったのは、日本のことだった。東南アジアからの不法滞在者やドラッグ密輸が
もっともっと問題になるのは遠い先のことでもあるまい。
そうしたときに、マリアの勇気に共感した気持ちを皆が思い出せるのだろうか。
(2006/07/17)
----------------------------
近年日本でも話題になる、体内にドラッグを詰めて密輸する運び屋の物語。
イエス・キリストの母マリアの処女懐胎にもひっかけてあるんじゃないかと思う題。
ヒロイン、マリアはコロンビアのバラ工場で働く。
一日中立ちっぱなしでバラのとげを取り、箱詰めをして、アメリカに輸出する。
安くて過酷な単純労働、でも、これしか労働需要がない。
需要と供給の資本主義社会に組み込まれたまずしい南米の国の日常。
考えてみると、バラとドラッグになんら違いはない。
どちらも、輸出用の、世界経済に組み込まれてしまった需要だ。
運び屋のコロンビア側元締めに限らず、
コロンビア人たちのドラッグに対する感情は冷めている。
それは危険な麻薬ではなく単なる換金商品だ。
映画はサスペンスフルではあるが、意外と静かに進み、終わる。
う〜ん。。
ハイリスク・ハイリターンの仕事しかないコロンビアや
麻薬問題の根の深さを考えさせられはしたが、それよりも、どんなことがあっても
女は生きていく、結局、ヤバイ仕事でもやってみたもん勝ち、、って印象が否めない。
新たな道を歩みだすマリアを待つのは、不法移民の道だ。
それでもアメリカにはまだ夢と希望がある、と映画は言う。
嫌味なくらい、コロンビアに戻るブランカは、ブスで進歩がなく自分勝手で、
一方、アメリカに希望を見出すマリアは、美人で勇敢で誠実である。
アメリカは今後も、ドラッグと不法移民があとをたたないだろう。
需要があるかぎり、入りつづけるだろう。
そして思ったのは、日本のことだった。東南アジアからの不法滞在者やドラッグ密輸が
もっともっと問題になるのは遠い先のことでもあるまい。
そうしたときに、マリアの勇気に共感した気持ちを皆が思い出せるのだろうか。
(2006/07/17)
----------------------------
 みて大正解の映画! スタイリッシュな映像と、静かに胸にしみる優しさ。
日本の小津監督を尊敬しているそうで、そういう感じはよく伝わる。
でたらめで生真面目。
なんのへんてつもないようで、とってもオカシイ。
大人の責任もない、将来や仕事、お金の心配もしなくてよい、恋とか愛とか
女の子にもまだあまり興味がない、でも、もう子供でもないし、いろんな不満につぶされそう、、
そんな14才の、単純でいて複雑な「時」を掬い取っている。
留守番をまかされた14才の少年ふたり。
お菓子を食べながらテレビゲームに興じ、母親が置いていったお金でピザを注文する。
隣に住む娘がオーブンを借りに来る。
30ぐらいのピザ屋の配達人が居座る(少年たちがいちゃもんをつけて、料金不払いを告げたから)
日常の怒りや緊張、ぎこちない4人のあいだにコミュニケーションが生まれる過程が
心憎いほど上手い。
わざとらしくなくていつのまにか映画にひきずりこまれる。
この午後が無かったら、主人公の少年は、全く違う大人になるだろうなあ。
この午後が無かったら、彼は嫌なかんじの若者になるんだろうなあ・・
カモの絵はトラブルの元であり、かつ、幸せと希望と夢の象徴だ。
ピザ配達人さんの幸せを心から願うよ〜!
おかあさんの登場する最後がまた笑える。
#十三の第七藝術劇場で11人の観客。。あぁ、もっと多くの人に見てもらえたら。
無理やり(笑)友人をひとり連れていったが、気に入ったらしく
ふふ、ラテンアメリカ映画、布教1。
(2006 9/3)
----------------------------
みて大正解の映画! スタイリッシュな映像と、静かに胸にしみる優しさ。
日本の小津監督を尊敬しているそうで、そういう感じはよく伝わる。
でたらめで生真面目。
なんのへんてつもないようで、とってもオカシイ。
大人の責任もない、将来や仕事、お金の心配もしなくてよい、恋とか愛とか
女の子にもまだあまり興味がない、でも、もう子供でもないし、いろんな不満につぶされそう、、
そんな14才の、単純でいて複雑な「時」を掬い取っている。
留守番をまかされた14才の少年ふたり。
お菓子を食べながらテレビゲームに興じ、母親が置いていったお金でピザを注文する。
隣に住む娘がオーブンを借りに来る。
30ぐらいのピザ屋の配達人が居座る(少年たちがいちゃもんをつけて、料金不払いを告げたから)
日常の怒りや緊張、ぎこちない4人のあいだにコミュニケーションが生まれる過程が
心憎いほど上手い。
わざとらしくなくていつのまにか映画にひきずりこまれる。
この午後が無かったら、主人公の少年は、全く違う大人になるだろうなあ。
この午後が無かったら、彼は嫌なかんじの若者になるんだろうなあ・・
カモの絵はトラブルの元であり、かつ、幸せと希望と夢の象徴だ。
ピザ配達人さんの幸せを心から願うよ〜!
おかあさんの登場する最後がまた笑える。
#十三の第七藝術劇場で11人の観客。。あぁ、もっと多くの人に見てもらえたら。
無理やり(笑)友人をひとり連れていったが、気に入ったらしく
ふふ、ラテンアメリカ映画、布教1。
(2006 9/3)
----------------------------
 すげぇメキシカン!
ぎんぎんに荒く激しく、まったりもったりと脱力して。
「ダック・シーズン」は、日本でも作れる映画だけれど、これは絶対に日本じゃありえん。
誰もが恐れる財界の大物、オスカル・カボスがゴルフボールを踏んでひっくり返り、
脳震盪を起こしてしまったことから、てんやわんやの物語が始まる。
タランティーノのレザボア・ドックスやパルプ・フィクションをわたしは思い出したが、
タランティーノほどスタイリッシュではない感じ。
むちゃくちゃで、なんでもアリで、ベタな笑い満載、
日本では差別表現になりそうな苛めや、下ネタで笑わせる下品さ。
生々しい残虐シーン、いっちゃってる人たち、
すまんです、わたし、けっこうこういうのが好きで、、ひぃ〜っひっひ、大笑いしてしまったが
館内で笑っていたの、わたし以外はみんなラテンアメリカ人かも?(爆)
よくある「取り違え」ものなんだが、これが実におかしく感じるのは、
いかにも物語!って感じの語り口と、脱力ふたり組がいいんです。
ジャックと、彼の親友のムド。 このふたりが深刻な状況なのに妙にまったりしていて(笑)。
無関係な人が巻き込まれて、殺されちゃったり、ひどい目に合ったり、、
ま、この映画に正義を求めちゃいかんです。。
たぶん、そこら辺が気になる人は、この映画を見たら嫌〜な気分になるでしょう。
(2006 9/8)
----------------------------
すげぇメキシカン!
ぎんぎんに荒く激しく、まったりもったりと脱力して。
「ダック・シーズン」は、日本でも作れる映画だけれど、これは絶対に日本じゃありえん。
誰もが恐れる財界の大物、オスカル・カボスがゴルフボールを踏んでひっくり返り、
脳震盪を起こしてしまったことから、てんやわんやの物語が始まる。
タランティーノのレザボア・ドックスやパルプ・フィクションをわたしは思い出したが、
タランティーノほどスタイリッシュではない感じ。
むちゃくちゃで、なんでもアリで、ベタな笑い満載、
日本では差別表現になりそうな苛めや、下ネタで笑わせる下品さ。
生々しい残虐シーン、いっちゃってる人たち、
すまんです、わたし、けっこうこういうのが好きで、、ひぃ〜っひっひ、大笑いしてしまったが
館内で笑っていたの、わたし以外はみんなラテンアメリカ人かも?(爆)
よくある「取り違え」ものなんだが、これが実におかしく感じるのは、
いかにも物語!って感じの語り口と、脱力ふたり組がいいんです。
ジャックと、彼の親友のムド。 このふたりが深刻な状況なのに妙にまったりしていて(笑)。
無関係な人が巻き込まれて、殺されちゃったり、ひどい目に合ったり、、
ま、この映画に正義を求めちゃいかんです。。
たぶん、そこら辺が気になる人は、この映画を見たら嫌〜な気分になるでしょう。
(2006 9/8)
----------------------------